| |
|
|
|
| 33 | ヨナクニカラスバト | 魚釣島 | |
| 参考 | ヨナクニヒヨドリ | ||
| 参考 | リユウキユウカツオドリ | 南小島 | |
| 参考 | リュウキュウカラスバト | 絶滅 | |
| 35 | リュウキュウキジバト | 魚釣島 | 留鳥 |
| 36 | リュウキュウクロアジサシ | 魚釣島 | 留鳥 |

典拠:写真集・「沖縄の野鳥」(昭和58年)、琉球新報社編・池原貞雄監修。
記事:58頁【奄美・沖縄鳥類目録】、魚釣島(繁殖)。(おそらく本亜種であろう。)留鳥。
山林に生息。
|
(Columba janthina)の1亜種。種カラスバトには3亜種あり、本亜種は八重山諸島の石垣島、西
表島、与那国島の森林地域に留鳥として分布する。個体数についての資料はほとんどない。
janthina)に類似しているが、体の金属光沢が少ない。また、嘴峰長が短い(清棲(1965)による
と、嘴峰長は基亜種の19〜21mmに対し、本亜種は18〜21mm)。
る。本亜種は、八重山諸島の石垣島、西表島、与那国島に留鳥として分布する。
く、ほとんどわかっていない。
現在は数が少ない。石垣島と西表島にはかなり生息していると考えられる。
減少に直接つながる。森林面積が減少している石垣島や、他の面積の小さい島では農地開発やレジ
ャー開発による森林伐採が絶滅に直結するおそれが強い。
(187ha)が設定され、1992年には西表島の中央山岳部を中心に国設西表鳥獣保護区(3,841ha、う
ち特別保護地区2,306ha)が設定された。国の天然記念物。


| 典拠:尖閣列島採集記3.【上陸第一歩】(「尖閣研究」http://pinacles.zouri.jp/bunken/
tawada1.htm )、原文は多和田真淳「尖閣列島採集記」、琉球新報(17 回連載)1952 年6月29
日〜7月15 日
記事:何千何万とも数え知れぬリユウキユウカツオドリが一度に飛び立ちギヤギヤ鳴きながら糞 爆の雨を降らし、右の岩かげ左の岩かげ、山の後へと飛び交い、飛び去り飛び来る、その様は筆 舌につくせるものではない。 |

典拠:《尖閣列島採集記8、(「尖閣研究」http://pinacles.zouri.jp/bunken/tawada6.htm)、
原文は多和田真淳「尖閣列島採集記」、琉球新報(17 回連載)1952 年6月29 日〜7月15 日》
リユウキユウカラスバト(魚釣島)
記事:「リユウキユウカラスバトは山羊の様な鳴声で木から木へ飛び回つているが、感が早くて
中々射てなかつた。」
|


| 1)絶滅(EX)
和名: リュウキュウカラスバト 分類: ハト目ハト科 学名: Columba jouyi(Stejneger, 1887) 英名: Ryukyu Wood Pigeon カテゴリー: 絶滅(EX) 環境省カテゴリー: 絶滅(EX) 形態: 全体的に黒色で頭頂はいくらか紫がかる。後頚は緑色でその下に白班がある。腰や胸にも 緑色の金属光沢がある。嘴は青色で脚は暗赤色。 近似種との区別: カラスバト(C. j. janthina)より大型で嘴の青色、後頚の大きな三日月白帯 が大きな特徴。 分布の概要: 沖縄諸島と南北大東島に記録が見られる。沖縄諸島では1887年2月に沖縄島北 部のKun―chan(国頭)で1個体の採集記録(タイプ標本)がみられる他、その後那覇や首里など 多数の捕獲記録が見られる。沖縄島周辺離島では、伊平屋島・伊是名島・屋我地島・座間味島な どでも1904年4月―7月にかけて採集された記録がみられる(Ogawa 1905)。大東諸島 では1922年9月に折居彪二郎氏によって南大東島から12個体、北大東島から2個体の捕獲 記録が見られる。なお、折居氏が1936年に南大東島大池の中島で採集した記録が本種の生存 が確認された最後の記録となっている。 生態的特徴: 主として常緑広葉樹林で生息していたと言われているが、詳しいことはわかってい ない。 学術的意義・評価: カラスバトの種分化や遺伝的変異を研究する上で貴重な存在である。 特記事項: 沖縄諸島、大東諸島の特産種。 原記載: Stejneger, 1887. Am. Nat., 21 : 583. (Kunchan, Ryukyu Is.). 参考文献: 環境庁編,1991.日本の絶滅のおそれのある野生生物−レッドデータブック− 脊椎動物編.(財)日本野生生物研究センター,東京. 環境省編,2002.リュウキュウカラスバト._改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物−レ ッドデータブック− 2 鳥類”,(財)自然環境研究センター,東京,30. 小林桂助,1983.原色日本鳥類図鑑.保育社,大阪,174. |

典拠:写真集・「沖縄の野鳥」(昭和58年)、琉球新報社編・池原貞雄監修。
記事:58頁【奄美・沖縄鳥類目録】、魚釣島。留鳥としてごく普通に生息。
|

典拠:写真集・「沖縄の野鳥」(昭和58年)、琉球新報社編・池原貞雄監修。(58頁【奄美・沖
縄鳥類目録】に記載)
記事:魚釣島。留鳥としてごく普通に生息。
|
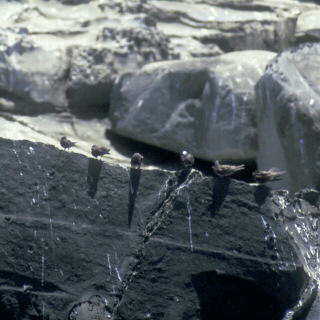


|
|


