��t�����̎��R

��t�����̋�ɕ������i�T�j
������������������������������������������������������������������������������
�T���R�E�`���E
��������������������������������������������������������������������������������
���z�F�쏬��
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

�T���R�E�`���E�Y����
Yachoo! �I�����C���쒹�}��
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

�T���R�E�`���E������
Yachoo! �I�����C���쒹�}��
�T���P�F�u��t�E�쏬����K�˂āv�r����Y�E������ƁE��Ԙ�
1974�N9�������A������w���16���|42��
�T���R�E�`���E�@�쏬��
|
������������������������������������������������������������������������������
�i16�j �V�}�A�J���Y
��������������������������������������������������������������������������������
���z�F�쏬��
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

Yachoo! �I�����C���쒹�}�Ӂ|����̈��p
�T���F�ʐ^�W�E�u����̖쒹�v�i���a58�N�j�A�����V��ЕҁE�r����Y�ďC�A
54�ʼn����E���꒹�ޖژ^
�u�V�}�A�J���Y�A�쏬���|�����A���Ȃ��B�v
|
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

Yachoo! �I�����C���쒹�}�Ӂ|�@�@����̈��p
�B�e�҃R�����g �����̃A�J���Y�������܂����B��Ŏʐ^������Ɨǂ��킩��Ȃ����̂���A�V�}�A�J���Y�����
�̂��Ȃ��B
����: �Y ����ɂ͊D�F��������A�w������܂ł̐ԐF���͔����A���F�ł���B�z��������͊D���F�łȂ����Ă�
��B����A�J���Y�ɔ�ׂ�Ɣ����ׂ͍��B���͍����F�Œ����F�̉H��������B�ߊ���������B�A�͔������A�����
�艺�̉��ʂ͂��Ԗ��̂��钃���F��ттĂ���B
����: �� ����
����: �c��(�ᒹ) �����畠�ɂ����āA���ɘe�ɂ͔g�����������B
���� �Ⴂ���ŃM�`�M�`�M�`�Ɩ��B
�̉a ���Ă�����A�t���ςɎ~�܂��Ă��鍩������ł���B�u�͂�ɂ��v���s���B
�ɐB: ������v�w 5�`7���ɔN��1��s���B�Ԃœn���Ă���̂͂��̂܂ܔɐB���A�P�Ƃœn���Ă������͎����l����
��܂Ś���B��v��Ȃł���B
�ɐB: ����� ���ɖ��������M�̒��ɑ������B������4�`6��1��1�����Y������B
�ɐB: ������琗 �Y�͕������̎��ɂ����a����B14���Ԃśz���i�ӂ��j���A14���ő����B
���z ���k��B�A�W�A�̉��сE�����тŔɐB����B�~�G�̓C���h�Ⓦ��A�W�A�ɓn���ĉ߂����B���{�ł́A�F�{���A
���������ŔɐB�̋L�^������A�قږ��N�ɐB���Ă���Ƃ����B�쐼�����ł͗ǂ������i��N���H�j�n����ɂ́A��
�{�C���̓��ׂ�쐼�����ŗǂ�������B
��������������������������������������������������������������������������������
�i17�j �X�Y��
��������������������������������������������������������������������������������
���z�F�쏬��
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

�T���F�ʐ^�W�E�u����̖쒹�v�i���a58�N�j�A�����V��ЕҁE�r����Y�ďC�A
54�Ł|�����E���꒹�ޖژ^
�u�X�Y���A�쏬���|�����Ƃ��đ������B�B�v
|
������������������������������������������������������������������������������
�i18�j �Z�O���A�W�T�V
��������������������������������������������������������������������������������
���z�F�쏬���E�k�����E�吳��

�Z�O���A�W�T�V�ƃI�I�A�W�T�V�̏W�c�c���|�k�����A
�u����̖쒹�v41�ŁA���a58�N

�k�����̃Z�O���A�W�T�V���a38�N�i1963�N�j
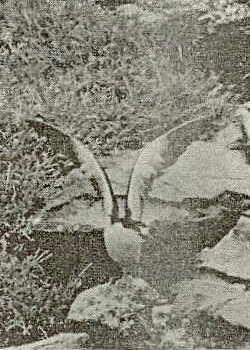
�k�����̃Z�O���A�W�T�V
��t�����������i���a�T�T�N�Q���A����J�����j

�k�����̃Z�O���A�W�T�V
�u�����̎��R�ƕ��v�ō��ǓS�v
�T���F�u����̔鋫��T��v�i33�Łj���ǓS�v���E����V��Ё@
�i�吳���j
�@�ߑO�Z���A�O���ɐԔ����i�ꖼ�吳���j��������Ƃ����D���̐��ɁA��їE��ŋN���オ
�����B���̓��́A�����ɂ���C�̌Ǔ��Ƃ��������������A���Ƃ������́A�ނ���C���ɓ�
���������傫�Ȋ�ʂƂ����������K����������Ȃ��B�ʐρZ�E��ܕ����L���A�W�����l���[
�g���B�C������ʂ��Ƃ��т�������A�́A���邩��Ɋ���Ȍ`�������Ă���B���̕����Ƃ�
���Ă���C�����A��H�ƂȂ��D�̋߂���ʂ�߂��čs���B�㗤�ł��Ȃ��̂ŁA�ł��邾���D
�𓇂ɋ߂Â��Ė]�����ł̂������Ƃɂ����B
�@�]�����Ŋώ@�����Ԕ����̊C���̓Z�O���A�W�T�V�A�J�c�I�h���A�N���A�W�T�V�ŁA������
�̋��߂锒���A�z�E�h���̎p�͓�����Ȃ��B�J�c�I�h���ƃA�W�T�V���Ԃ̏Z�ݏ�̋敪�́A
�k�����̏ꍇ�Ɏ��Ă���B�i�u����̔鋫��T��v���ǓS�v���E����V��ЁA�P�O�Q�ŁA��
�l�̓A�z�E�h�������蕷������y�������|�A�z�E�h�������߂āz�j
�i�쏬���j
�@�������a��\���N�Ɠ�\���N�ɒ������������̏ɔ�ׂāA�J�c�I�h���A�Z�O���A�W�T
�V�Ȃǂ������������Ă��邱�Ƃɋ������ꂽ�B���̂悤�ɗ��l����ē��̊C���͔N�X��
���̈�r�����ǂ�̂��낤�B�����̂ǂ̓��ł����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��M�d�ȊC���̊y����
�r�炳��A��Z�N�O�̋���͂ǂ̑s�ςȊC���̂��������́A�قƂ�ǂȂ��B�����A����
�ł����߂ė��������W�҂́A�k�����̃Z�O���A�W�T�V�̗����Ɉ��|����Ă���B
�i�u����̔鋫��T��v���ǓS�v���E����V��ЁA�P�O�T�ŁA��l�̓A�z�E�h�������蕷��
����y�������|�A�z�E�h�������߂āz�j
�i�k�����j
�@�k�����A�쏬���Ƃ��ɐ������̊C�����Z��ł���̂ŁA���t�͌Â����炱�̗��������
���đ��ɒ����ƌĂ�ł���B�������́A�킸����Z�Z���[�g����������Ă��Ȃ����A������
�Z��ł���C���̕��z�́A�쏬���Ƃ͒����������ނ����قȂ��Ă���B���Ȃ킿�A�쏬
���̓J�c�I�h������ł���̂ɔ����A�k�����ł̓Z�O���A�W�T�V���������߂Ă���B
�@�k�����̓씼���̊ɂ₩�ȎΖʂ́A�Z�O���A�W�T�V���Ɛ肵�Ă���A�N���A�W�T�V�͉���
�̊₾�ȂɁA�J�c�I�h���͎�ɐ��݂���ѓ�݂̃K�P���̎Ζʂ�A��ǂɂȂ풣�������
�ďZ��ł���B�C���̕����������Ĉ������ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�i�u����̔鋫��T��v���ǓS�v
���E����V��ЁA�X�R�ŁA��O�͐�ł̓��X�̋��فy�C���̍U���z�j
|
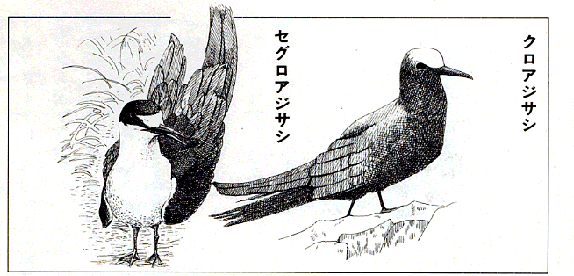
�u��������H�����b�v43��

�Z�O���A�W�T�V�̃��[���i�k�������a�Q�W�N�j
�u���R�Ƃ̑Θb�v9�ŁE���ǓS�v

�Z�O���A�W�T�V�E�k����
�E��t�������������Ҏ[�ψ���E
��t����i�ɂ��āE��t�����̓��X�i�Q�j�k�����E�쏬��
�Z�O���A�W�T�V�̐��ԁi�k�����j
�@���ǂ��́A���������������Ă���C���̐���A���̏K���̋������鎖���ɋ������ꂽ�B�����
�ʼnf��ł����ڂ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ������C���̌Q�W�A���ɂ������̊C�������ł���A���̂���
�ɓ����͂��������A���Ȃ��Â����ƂȂ�B�܂��₦�����̉J���~���Ă���B�n��ɂ́A�E�Y����
�����悤�ȃZ�O���A�W�T�V�̃q�i���A���悻�O�Z�Z���`�����̊Ԋu�ŎU�݂��Ă���A���ƒn���
��߂��e�q���̐����₩�܂����A�킸����Z���[�g������Ă��A���ǂ��̑吺���ʂ��Ȃ��قǂł�
��B
�@���ł���e���̒��ɂ͖җ�Ȃ̂����āA�l�̊���߂����Đ��ʂ���˓����A����������߂Ĉ�
��������̂�����B�܂������ܑ��ʂ���U�����Ă�����̂�����B�����ƂЂǂ��̂́A�����ƂŃM
���[�Ƒ吺���o���Ɠ����ɁA���Ԃ��Ă���X�q���͂����Ēʂ蔲���Ă����̂ŁA��⊾�̂����ǂ�
���ł������B
�@�\���l�̐l�Ԃ��A���������ŃZ�O���A�W�T�V�̐e���ɍU������Ă��邪�A��������l�œ����ɁE
�������ނƁA���̉s���������ŃA�W���h���悤�ɁA�����҂ǂ�����Ă��܂��ł��낤�B����
������ɂ�����Ă���ƁA����ɏ�畑������āA�l�Ԃ̎��ӂ̓Z�O���A�W�T�V�ɕ�͂����
���܂��B�����Ȃ�ƁA�������C���̒��Ԃɉ�����ꂽ���������邪�A������Ƃ����Ĉ��S�͂ł���
���B��͂�s�C���ŁA�g�̖т��悾�v���ł������B�C���̕����������Ĉ������ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�i�u����̔鋫��T��v���ǓS�v���E����V��ЁA
�X�R�|�X�S�ŁA��O�͐�ł̓��X�̋��فy�C���̍U���z�j
http://contents.kids.yahoo.co.jp/zukan/birds/card/0233.html
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

���@��
���� �`�h���� �J������
�w�@��
Sterna fuscata
���z�ƋG��
���ꌧ�암�̓��A�����s���}�������ȂǂŔɐB����Ē��B
�@��
�C�m�Ɠ���
�S�@��
��40.5cm�i�A�W�T�V����j
����
�N���b�A�N���b
�ʐ^�B�e�n
���ꌧ���̐_��
���@��
�Ђ����ƁA�̂ǂ��畠�������B������w�ʂɂ����Ă͍��B�悭���Ă���}�~�W���A�W�T�V�́A�w��
���D�F�A�Ђ��������̏�܂ł������̂ŋ�ʂł���B�O�m�̖��l���ŏW�c�ɐB����B���͂���
���A��̏�ɒ��ڗ����Y�ށB�����͎��ӂ̊C�łƂ�B�ق��̃A�W�T�V�ނ�荂���Ƃ��납�珬����
�Q��Ɍ������ă_�C�r���O���A�������ł͂���łƂ炦��B
http://www.pref.okinawa.jp/okinawa_kankyo/shizen_hogo/rdb/sp_data/g-00971.html
�Z�O���A�W�T�V�i��j code g-00971
�a�� �Z�O���A�W�T�V
���� �`�h���ځ@�J������
�w�� Sterna fuscata nubilosa Sparrman, 1788
������
�J�e�S���[ ��
������
�J�e�S���[
���� �p��:�@Sooty�@Tern
�S��40cm�A���d�R�����̒���_���ɉĒ��Ƃ��ēn���W�c�ɐB���Ă���B�����̒n��̗m��ł́@
����芪����@������A�a�����̂��ǂ�������B
���L��:�@Sparrman,�@1788.�@Mus.�@Carlsnianum,�@fasc.�@3,�@No.63�@("Finlandia"�@error�@for
�@India).
�Q�l����:�@���c���X,�@1980.�@�V�Œ��ތ��F��}��,�@�u�k��,�@����.
����쒹�������,�@1993.�@�������ꌧ�̖쒹,�@����o��,�@�Y�Y.
�R�K�F��,�@1980.�@���{�̒��ނƂ��̐���.�@�����[,�@����.
(��)���{���ޕی�A����,�@1988.�@��630�}��,�@(��)���{���ޕی�A��.
http://www.sanshin-ci.co.jp/index/photo1/MichaelmesCay/page_thumb10.html
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

http://www.sanshin-ci.co.jp/index/photo1/MichaelmesCay/page_thumb9.html
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

http://www.gt-works.com/yachoo/zukan/tori/kamome/seguroajisasi.htm
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

�ʐ^ ���� �ĉH �ʐ^ ����
�B�e�� �ђ� ���
http://www.mnx.ne.jp/~fab8727/mc/mcseguroajisasi.htm
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

�@�쒹���ւ�99�N��5��8������9����2000�N��5��29������31����2�x�s�����Ƃ��ł����B���������
�����̃Z�O���A�W�T�V���ώ@�ł��A�R���j�[�̋K�͂����܂������̂��������B99�N�̊ώ@�ł͗���
�����قƂ�ǂł��������A2000�N�̊ώ@�ł͂قƂ�ǂ����̏�ԂŁA���傫�Ȑ��H��c���Ƃ���
�����̂�����ꂽ�B�ݓ��҂ɂ��ƁA��N3�����{����ɐB���n�܂�A8����t�܂ő����Ƃ����B
�Z�O���A�W�T�V�̃R���j�[�͊C�݂̍��l����O���o�C�q���K�I�Q���n�܂ŕ��z���A�c�����x�͍�
���A�쓌�[���ӂ��琼�ւ��悻�P�q�㑱���Ă����B��ʐ^�̂悤�ȃR���j�[�����X�����Ă�����
�ŁA�ɐB���͌��������Ȃ��B���Ȃ����ς����Ă�5000�ȏ�̑�������̂ł͂Ȃ����낤���H�@��
�͋ɂ߂ĒP���ł���A�����Ƃ����ق����K���낤�B���͍��̏�Ƀ|�c���ƒu����Ă��邾������
���B�Z�O���A�W�T�V�̔ɐB�n�ɂ��āA�l�͑��ɗ����������������Ƃ��Ȃ��B�������A�쒹���͓�
�{�ōő�̃Z�O���A�W�T�V�ɐB�n�ł͂Ȃ����Ǝv����B
 �����s���H �����s���H
�@�����Ǝv����s�����ώ@���邱�Ƃ��ł����B�Ƃ肠�����ʐ^�̂悤�Ȋi�D�ŃA�s�[���H���Ă�
���B�Њd�Ȃǂ͌������{�œ˂��Ă����̂ŁA�قڊԈႢ�Ȃ������s���ł��낤�B�ݓ��҂ɂ��ƁA
��N8�����܂ŔɐB���Ă���Ƃ̂��ƁB����2�H�͖����ɐB���邱�Ƃ��ł����̂��낤���H

�����Ɛ� �@99�N�ɗ������������ɂ́A�܂����̏�Ԃ̂��̂���������ꂽ���A2000�N�ɗ�����
�������ɂ͂قƂ�ǂ����̏�Ԃ������B�l�͔n�����I�@���Ɨ��̃A�b�v���B��̂�Y�ꂽ�c�B�Ƃ�
�����B�������̂����邪���ɗǂ��Ȃ��B�ꏊ�͈Ⴄ���A���Ɨ��̎ʐ^�͗������ŎB�e�ς݂ł�
��B
�B�e�F��i�@�쒹���i2000.5.30�j
�����i�@�쒹���i1999.5.9�j
http://www2.odn.ne.jp/wildbird/ext_12.htm
http://rca.open.ed.jp/oh/bird/book/ohb0127.html

�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

http://www.kingfisher.jp/alcedo/bird_g/cairns2/2-163-34.jpg
�i���������t�����̂��̂ł͂���܂���j
 �@�@�@ �@�@�@
�Z�O���A�W�T�V
�ʐ^���@�B�e�F N. MATSUDO�@�@2003�N4��17���@�E�͏o�T�s��
�ȉ���http://www.pref.okinawa.jp/okinawa_kankyo/shizen_hogo/rdb/sp_data/g-00971.html�̋L
��
�Z�O���A�W�T�V�i��j
code g-00971
�a�� �Z�O���A�W�T�V
���� �`�h���ځ@�J������
�w�� Sterna fuscata nubilosa Sparrman, 1788
�J�e�S���[ ��
������
�J�e�S���[
���� �p��:�@Sooty�@Tern
�S��40cm�A���d�R�����̒���_���ɉĒ��Ƃ��ēn���W�c�ɐB���Ă���B�����̒n��̗m��ł́@
����芪����@������A�a�����̂��ǂ�������B
���L��:�@Sparrman,�@1788.�@Mus.�@Carlsnianum,�@fasc.�@3,�@No.63�@("Finlandia"�@error�@for
�@India).
�Q�l����:�@���c���X,�@1980.�@�V�Œ��ތ��F��}��,�@�u�k��,�@����.
����쒹�������,�@1993.�@�������ꌧ�̖쒹,�@����o��,�@�Y�Y.
�R�K�F��,�@1980.�@���{�̒��ނƂ��̐���.�@�����[,�@����.
(��)���{���ޕی�A����,�@1988.�@��630�}��,�@(��)���{���ޕی�A��.
������������������������������������������������������������������������������
�i19�j �c�o��
��������������������������������������������������������������������������������
���z�F���ޓ��E�쏬��

�T���P�F�@�u����̔鋫��T��v���ǓS�v�A����V��ЁA�V�V�ŁA���͓쏬���Ƌ��ޓ��̐���
�����y�쒹�ƒ��̐��������z
�@���ޓ��ɂ͏\����̖쒹��������B���̎�ނ́A�܂ɂӂ�ďq�ׂĂ������B�쏬���̖쒹
�́A�c�o���A�����E�L���E�c�o���̂ق��́A�قƂ�nj����Ȃ��B
�@�����ɂȂ��Ď����H���쒹�ł��A�q�i����Ă�ɂ͒����K�v�ł���B�쏬���̓��̃c�o��
�́A��Ƀn�G�Ɖ��H�ׂĂ��邪�A����Ɋ₾�炯�̓쏬���ɑ����̃c�o�����n���ė��Ă��A��
��͂����܂��H���s���ɂ��������āA���ֈړ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�B��������������
�쏬���̃c�o���̐��́A���ޓ��ɔ�ׂ�ƒ��������Ȃ��B
|
�c�o���i���ޓ��E�쏬���j
�@���ޓ��ɂ͏\����̖쒹��������B���̎�ނ́A�܂ɂӂ�ďq�ׂĂ������B�쏬���̖쒹�́A
�c�o���A�����E�L���E�c�o���̂ق��́A�قƂ�nj����Ȃ��B
�@�����ɂȂ��Ď����H���쒹�ł��A�q�i����Ă�ɂ͒����K�v�ł���B�쏬���̓��̃c�o��
�́A��Ƀn�G�Ɖ��H�ׂĂ��邪�A����Ɋ₾�炯�̓쏬���ɑ����̃c�o�����n���ė��Ă��A����
�͂����܂��H���s���ɂ��������āA���ֈړ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�B��������������쏬
���̃c�o���̐��́A���ޓ��ɔ�ׂ�ƒ��������Ȃ��B�i�u����̔鋫��T��v���ǓS�v�A����V��
�ЁA�V�V�ŁA���͓쏬���Ƌ��ޓ��̐��������y�쒹�ƒ��̐��������z�j
��������������������������������������������������������������������������������
�i20�j �c�o���`�h��
��������������������������������������������������������������������������������
�c�o���`�h��
�o�T�F���ǓS�v�u����̔鋫��T��v46�Ł@���a�Q�T�N�R��
�c�o���`�h���i���ޓ��j
�@�D���ɓ���Ɠ����Ɋ�������ߋ��������̂�����B�U��Ԃ��Č���ƁA����̓c�o���`�h���ł�
�����B���̏����͋��ޓ��Ɉ��Z���Ă���̂ł͂Ȃ��A�n��̓r���ɖ�������ł������̂Ǝv���
��B�i�u����̔鋫��T��v���ǓS�v���E����V��ЁA�S�T�|�S�U�ŁA���͐�t�̏��T�K
�y���̊C�̗H��D�z�j
�i�ȉ��̋L���ʐ^���Ɂu����̔鋫��T��v�Ƃ͖��W�ł��j
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

http://www2.odn.ne.jp/wildbird/add_52.htm#01
�`�h���ځ@�c�o���`�h����
�c�o���`�h���@�iGlareola maldivarum�j
�y�B�e�ҁz �m�D�l�`�s�r�t�c�n
�y�f�[�^�z�@ �c�o���`�h���@2000�N3��25�� ���ꌧ���d�R�S�^�ߍ���
�@�@�@�@�@�@PENTAX Z-1P smcPENTAX67M*6.7/800ED
http://contents.kids.yahoo.co.jp/zukan/birds/card/0219.html
�c�o���`�h��
�iC�jOsamu YUNOKI
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

���� �F���� �`�h���� �c�o���`�h����
�w���FGlareola maldivarum
���z�ƋG�߁F���{�e�n�ɗ����Ƃ��ďt�ƏH�ɓn������B
�@�� �F�C�݁A�͐�
�S���F��26.5cm�i���N�h������j
���� �F�N�����A�N����
���@���F
����������B�Ɩ{�B�ŔɐB�����L�^������B�������Ƒ����Z���A
��������A�����c�o���Ɏ��Ă��邱�Ƃ��疼�Â���ꂽ�B
��тȂ���Ńg���{�A�A�u�Ȃǂ̍������Ƃ炦�邦���̂Ƃ�����A
�c�o���Ɏ��Ă���B��ѕ����c�o���Ɏ��ăX�s�[�h�����邪�A
�H�����ƃO���C�f�B���O�����肩�����̂������ł���B
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

�c�o���`�h���@���璹�@Large Indian Pratincole
http://egkaz.sakura.ne.jp/tsubamechidori.html
http://www.pref.okinawa.jp/okinawa_kankyo/shizen_hogo/rdb/sp_data/g-00941.html
�c�o���`�h���i��}��j code g-00941
�a�� �c�o���`�h��
���� �`�h���ځ@�c�o���`�h����
�w�� Glareola maldivarum J. R. Forster, 1795
�J�e�S���[ ��}��
������
�J�e�S���[ ��
���� �p��:�@Indian�@Pratincole
�`��:�@�S����26cm�B�ĉH�͏�ʂ��ÊD�F���F�ŏ�����͔��������͍����B
�A�͔��F�����鉩�F�ō������C���ň͂܂��B���Ƙe�͉����F�ʼn��J���͌I�F�A
�ڐ�Ƌr�͍��F�ł���B�~�H�ł͚{�̂قƂƂ�ǂ����F�ōA�͒W�����F�ƂȂ�A
�������������s���ĂƂȂ�B
�ߎ���Ƃ̋��:�@���Đ��̍����Ȃǂ��ʼna�Ƃ��č̂�l�̓A�W�T�V�ނ�
�A�}�c�o���ނɎ��邪�A�{��͑S�̓I�ɑ��߂ŗ��̕����L�����߂Ɍ�����B
�܂���тȂ���L�����A�L�����Ɩ��B���Ă��Ă���Ƃ���ҏ�̔��H�Ə����
�y�є��̊�̔��������ڗ��B
���z�̊T�v:�@�{�B�E�l���E��B�E�ɓ������ɗ����Ƃ��ēn������B
�{�B�̐É����E���m���E���挧�Ƌ�B�̕������E�{�茧�ł�
�Ǐ��I�ɔɐB���Ă���Ƃ���Ă������A�k�C���ł��L�^���݂���悤�ɂȂ����B
�S���I�ɂ͗����ł��邪�ɐB�n�ł͉Ē��ł���B
�����ł͂���܂ʼn���E�{�Ó��E���l���E�^�ߍ����E�Ί_���Ȃǂɗ����Ƃ���
�n������Ƃ���Ă���B�ߔN����Ƌ{�Ó��y�шɍ]���ł͔ɐB�Ⴊ�m���Ă���B
�߉��̎�y�ьQ�Ƃ̕��z�̔�r:�@�c�o���`�h���ނ͐��E��17�킠��Ƃ���
���[���b�p�ƃA�W�A�암�A�I�[�X�g�����A�A�A�t���J�̊J�������Ӌ߂��̍��n���Βn�Ȃǂ�
��Ȑ����n�Ƃ��Ă���B�{��ɂ͈���͂Ȃ��߉���Ƃ��ăI�[�X�g�����A�ŔɐB���A
�Ăɂ̓j���[�M�j�A��C���h�l�V�A�Ȃǂɓn��@Stiltia�@isabella��A
�C���h���璆���쐼���܂ŕ��z���r���}��^�C�A�J���{�W�A�A���I�X
�Ȃǂł͗����Ƃ��Đ������Ă���@Glareola�@lactea�@������B
���ԓI����:�@�����E�����n����܂�ȗ��n�̂��鑐��̒Ⴂ�����Ȃ�
�Ђ炯���ꏊ�ɂ��ށB�ɐB���͏��R���j�[������B���͒n��ɐ��ڂ݂����菬�A
�L�k�A�͂ꑐ�A�ؕЂȂǂ��킸���ɕ~���B�P���Q�`�R�����Y�ށB
���͒W�����F�ňÊ��F�̔����ł�B�����͎��Y���ōs�����������͖�18���ł���B
�a�͔��ł��鍩�����тȂ���߂炦�邪�n��ł��̉a����B�����ȌQ�Ō����邱�Ƃ������B
�����n�̏���:�@�����E�����n�E��s���q���n�̒��̗��n�̂��鑐��̒Ⴂ�����A
�_�n�����y�эk�]������̔_�k�n�ȂǂЂ炯���ꏊ�B
�w�p�I�Ӌ`�E�]��:�@�A�W�A�̉��т���M�тŔɐB���A�m�F�����͈͂�
����A�W�A�A�C���h�A�����A�C�쓇�A���s�A��X���_�����A�t�B���s���A
�j���[�M�j�A�A�I�[�X�g�����A�ȂǕ��z��͍L���B���m��n�̗v�f�������ނł���B
�{��͈��킪���Ȃ��B���͏��Ȃ��Ȃ��疈�N�̂悤�Ɍ����ɓn�����A
�Ǐ��I�ł͂��邪�ɐB���Ă���n�悪����B
�����ɑ��鋺��:�@�{�����n���̑����r��n�ɐ��������ł��邽�߁A
�����ł͖����n��_�k�n�ȂǔɐB���̐����n�ƂȂ�n��͐l�דI�ɊJ���ꂽ
�ꏊ�ł���B���������āA���̗��p�͈ꎞ�I�Ōp���I�ł͂Ȃ����ߔɐB�n�Ƃ���
�s����ł���B�܂��琗���ɂ�����ɐB�n����̖쐶�������C�k��l�R��
���ЂƂȂ肤��B
���L��:�@J.�@R.�@Forster,�@1795.�@Faun.�@Indica,�@ed.�@2:�@11�@(ex�@Latham,�@"open�@sea,
�@in�@latitude�@of�@the�@Maldi-via�@Isles").
�Q�l����:�@B.�@F.�@King�@and�@E.�@C.�@Dickinson,�@1975.�@A�@Field�@Guide�@to�@the�@Birds
�@of�@South-East�@Asia,
Houghton�@Mifflin�@Company,�@Boston.
J.�@Mackinnon�@and�@K.�@Phillipps,�@1993.�@A�@Field�@Guide�@to�@the�@Birds�@of�@Borneo,�@
Sumatora,�@Java,�@and�@Bali,�@Oxford�@University�@Press,�@Oxford.
������,�@1991.�@���{�̐�ł̂�����̂���쐶�����|���b�h�f�[�^�u�b�N�|�@�Ғœ�����,�@
(��)���R�������Z���^�[,�@����.
���ьj��,�@1984.�@���F���{���ސ}��,�@�ۈ��,�@���.
�v�L�����E�R�{�W,�@1981.�@�{�ÌQ���̒��ޖژ^.�@���������,�@14:15-29.�@���ꐶ�����猤��
��,�@�ߔe.
���c���v��,�@1984.�@���������}��.�@����,�@���E������,�@����.
Mark�@A.�@Brazil,�@1991.�@The�@Birds�@of�@Japan,�@Christopher�@Helm�@and�@A�@&�@C�@Black,
�@London.
���{���w���,�@1974.�@���{���ޖژ^,�@�w�K������,�@����.
����쒹�������,�@1986.�@���ꌧ�̖쒹,�@����쒹������.
�����V��Е�,�@1983.�@�ʐ^�W����̖쒹,�@�������V����,�@����.
��������E���˓S��Y,�@1992.�@�ɍ]���̒��ޑ��ɂ���,�@�����ۋI�v,�@8:51-69.�@���ꌧ����
��������,�@�ߔe.
������������������������������������������������������������������������������
�i21�E�Q�l�j �c�~
��������������������������������������������������������������������������������
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂ł͂���܂���j

http://yasou.cocolog-nifty.com/b...f55.html
�Ɍf�ڂ���Ă����摜�ł��B
�T���F�@�u����̔鋫��T��v���ǓS�v���E����V��ЁA�V�W�ŁA���͓쏬���Ƌ��ޓ��̐���
�����y�쒹�ƒ��̐��������z
�L���F�@��ʂ̏�ɃA�}�T�M�̎S���̂�����B����̓c�~�Ƃ����ҋׂ̒��ԂɁA����Ȃ�������
��������|���ꂽ�̂ł��낤���B
|
������������������������������������������������������������������������������
�i22�j �@�j���g���i��ŁH�j
��������������������������������������������������������������������������������
���z�F�v�
�i���̎ʐ^�͐�t�����̂��̂Ƃ͖��W�ł��j

����v�ē��̕��̃T�C�g�ɂ��������̂ŁA���ꂳ�����Ă����{�Ƃ̂��ƁB
�ȑO�͂P�O�O�H�������Ƃ������Ƃł�����A���������{���������܂ꂽ�̂ł��傤�H
�������s���܂���B
�T���F �u����̔鋫��T��v���ǓS�v���E����V��ЁA�P�P�V�ŁA��l�̓A�z�E�h������
�蕷������y�������̍��́z
�@�������̓쐼���C�߂��ɁA���É�C�l�Y���̎��Ə�̐Ղ�����B�����͒����̏W��
�ǂ̎��Ƃɏ]�����Ă����l�тƂ̋��Z�Ղł��邪�A�G�؎G���ɂ������Đ̂̂���������
�͂Ƃ�ǂȂ��B
�@�������Ɉړ����������̋L�^������B�ړ����������̂����A�j���g���͖����\���N�i��
�����܁j�ɁA�����̖�l���n�������ۂɕ����������̂ł���B�����O�\�O�N�i���Z�Z�j
�܌��ɉ�������T�������{�����V�����̕i�w�n�w�G���x�\��S�j�ɂ��ƁA�j���g��
�͔ɐB���Ė쐶��ԂɂȂ��Ă����Ƃ����B
|

|







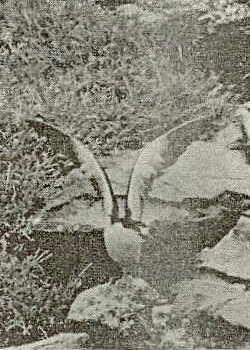

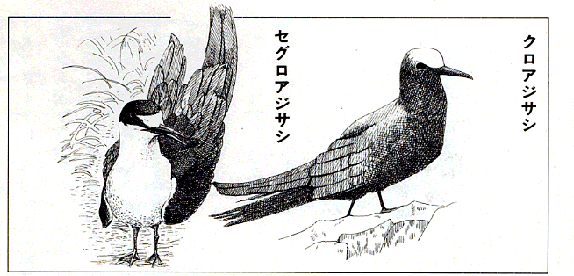







 �����s���H
�����s���H 


 �@�@�@
�@�@�@









